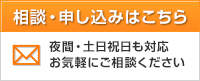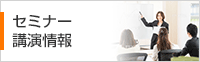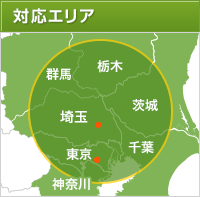契約書の内容
第1 はじめに
現代社会においては、個人の自由が保障されていることが当然の前提になっています。したがって、人が権利を取得したり義務を負ったりするのは、その人の意思によるときだけだ、と考えるのが原則です。これを「私的自治の原則」といいます。この私的自治の原則に基づけば、個人の意思に基づく限り、どんな内容の契約であってもいいということになります。
もっとも、すべてを個人の意思に任せると、その内容があまりにも社会的妥当性を欠く場合が出てきます。そこで民法は、契約の内容が「公の秩序又は善良の風俗(公序良俗)」に反する場合には、例外的に契約が無効になると定めています(民法90条)。たとえば、愛人契約や暴利による金銭の貸付などは、公序良俗違反で無効とされます。
その他にも、消費者契約法など個別の法律において、その内容が社会的妥当性を欠くとして無効となる契約類型を定めています。たとえば、消費者契約法10条は、事業者と消費者との契約で、消費者の利益を一方的に害する条項は無効であると規定しています。そして、この規定によって、借家契約における自然損耗の原状回復を借り手の負担とする特約が無効と判断された事例があります(京都地裁平成16年3月16日判決)。
第2 契約書の内容に関する注意点
1. 言葉遣い
契約書の体裁や言葉遣いには、決まったものはありません。ですから、いかにも法律文書というような難しい言葉である必要はまったくなく、わかりやすい平易な言葉を使えば十分です。
難しい言葉であろうと簡単な言葉であろうと、もっとも大切なのは、基準を自分たちに置いて契約書を作成しないということです。つまり、契約当事者でない第三者が普通に契約書を読んだとき、どう解釈されるかを考えて作成することに注意してください。たとえば、何も事情を知らない高校生などが見た時に「こういう意味だな」と理解できるようなものであればよいのです。
2. 何をどう書けばいいのか
契約書には、①誰が(主体)、②誰に対し(客体)、③いつ、どのような場合に(時制)、④何を(目的物)、⑤どうするか(行為内容)を、明確に書くことが必要です。
① 誰が(主体)
主体についての注意点は、義務者を主語にした方が、内容が明確になるので良いという点です。具体的にみてみましょう。
- △ 「乙が上記義務を怠ったときは、甲は、乙に対し、○○などの書面の交付を請求することができる。」
この書き方だと、甲が請求することができるだけで、乙はそれに対応する必要がないと見られかねません。そこで、
- ○ 「乙が上記義務を怠ったときは、乙は、甲の求めに応じて甲に対し、○○などの書面の交付をしなければならない。」
というように、義務者乙を主語にして書けばよいのです。
② 誰に対し(客体)
義務者を主体とすることに対応して、権利者を客体とし、それを明示するようにしましょう。行為の当事者両名を明示することで、やるべき行為がはっきりし、後の紛争予防になります。
③ いつ、どのような場合(時制)
契約書の内容に疑義が生じて後の争いにならないように、「いつ」「どのような場合」について明確に記載する必要があります。 その際、法律用語として使い方に一定のルールがある言葉がありますので、その言葉は正確に使用してください。たとえば、以下のようなものです。
(ア)「場合」と「とき」の使い分け
仮定的条件が2つ重なる場合、「場合」は大きい条件、「とき」は小さい条件で使用します
(イ)「直ちに」、「速やかに」、「遅滞なく」の使い分け
すべて「いますぐに」というような時間的即時性を求める言葉ですが、緊急度が高い方から、「直ちに」、「速やかに」、「遅滞なく」の順で使用します
④ 何を(目的物)
金銭について書く場合、算用数字を使用するときは、「¥200,000」や「金200,000」のように「¥」や「金」を数字の前に置いた方が改ざんを防げます。また、改ざんを防止するために、算用数字を使用せず、「二十万円」や「弐拾萬円」など漢数字を使用してもよいでしょう。
さらに、契約の目的物が物の場合には、いつ所有権が移転するのか、引渡し(占有移転)をいつにするのかについて明らかにしなければなりませんし、登記や登録のやり方・日程も決めなければなりません。
⑤ どうするか(行為内容)
①で述べたように、義務者が行うべき義務の内容を第三者が見てもわかるくらい明確に書きましょう。金銭の支払いを求めるときなど、こちらから請求する立場の場合は、できれば、相手方が義務を怠ったときのペナルティも書くとよいです。
なお、相手方に金銭の支払いを請求するなど積極的な行動を求めたりするのではなく、単に債務がないことを確認するなど相手方に積極的な行動を求めないときは、「認める。」とか「確認する。」という表現で十分です。
第3 具体的な契約条項
1.特約を定める
契約書にないことが起こったら困ると説明しましたが、多くの場合「こういう場合には、このように処理しましょう。」ということが民法やその他の法律で定められています。したがって、本当に「どうしたらいいか全く分からなくて困る。」ということはほとんどありません。
しかし、このような法律の規定は、「一般的にはこうした方が望ましい。」として定められたものです。そして、個々の契約の内容によっては法律の規定とは異なる処理をした方が望ましい場合もあります。そこで、契約を締結する際は、「法律の定めにしたがえば、このような処理になる。」ということを踏まえた上で、当事者がこれと異なる処理を望むのであれば、特別の定めをしておく必要があります。このような契約上の特別の定めのことを「特約」といいます。以下、実務上特に用いられることが多い①期限の利益喪失と、②解除について説明します。
2.期限の利益の喪失条項
(1) 期限の利益の喪失とは
「期限の利益」とは、“期限が到来するまでは、自己の債務を履行しなくてもよい”という債務者の利益のことをいいます(民法136条1項)。例えば、「平成○年○月○日に代金を支払う。」と規定された場合、この支払期限が到来するまでは、債務者は代金の支払いを猶予されることになります。
債務者に期限の利益があるということは、裏返せば、債権者は期限が到来するまで待たなければならないという不利益があることを意味します。しかし、債務を履行してもらえないという不安が発生したにもかかわらず、期限の到来を待たなければならないというのは不都合です。そこで、民法は、債務者側に一定の事由が生じた場合に、債務者は期限の利益を失い、債権者は直ちに履行を請求できることにしました。これを「期限の利益の喪失」と呼びます(民法137条参照)。
期限の利益を喪失する事由として、民法は、①破産手続開始の決定を受けたとき、②債務者が担保を滅失・損傷・減少させたとき、③債務者が担保提供義務を怠ったとき、の3つを規定しています。しかし、債権者としては、期限の到来を待っていることができない事情は、この3つ以外にもあることでしょう。そこで実務では、契約の内容や当事者の事情に応じて、債務を履行できなくなりそうな状況をあらかじめ想定して、期限の利益を喪失する事由を定めておくのが一般的です。このような定めを「期限の利益の喪失条項」といいます。
(2) 契約条項の定め方
期限の利益の喪失事由の定め方としては、「当然喪失条項」と「請求喪失条項」と呼ばれる方法があります。「当然喪失条項」とは、ある事由が発生した場合に、当然に期限の利益を喪失すると定める方法です。これに対して、「請求喪失条項」は、ある事由が発生した場合であって、債権者から請求があったときに期限の利益を喪失すると定める方法です。
この2つの使い分けですが、すぐに債務の履行を請求しなければ債権回収できなくなるおそれがあるような緊急性が高い事由については当然喪失条項、そうでない事由については請求喪失条項、とするのが一般的です。しかし、あくまで一般論ですので、それぞれのメリット・デメリットを踏まえて、使い分けると良いでしょう。例えば、当然喪失条項は、債権者が何もしなくてよいというメリットがあります。しかしその反面、期限の利益の喪失事由が発生した時点から、自動的に消滅時効が進行してしまうで、請求喪失条項と比べ早く消滅時効が完成し、債権が消滅する危険性があります(消滅時効についてはコラム「債権管理と消滅時効」参照)。
3.解除条項
「解除」とは、一度成立し有効な契約を、事後的になかったことにすることを言います。実務上も、当事者間に何らかのトラブルが生じて、契約を“キャンセルしたい”“破棄したい”というケースがよくあります。では、どのようなケースであれば、解除することができるでしょうか。以下、解除に関して契約書でよく規定される例を紹介します。
① 解除原因の設定
解除の代表例は、履行遅滞に基づく解除です(民法541条)。例えば、「債務者が、約束どおりお金を払ってくれない」といったケースです。その他にも、民法は契約類型ごとに解除原因を定めています。このような解除権を発生させる事由(「解除原因」)が法律によって定められているものを、「法定解除」といいます。
一方で、民法では契約で解除原因を定めることができると規定しています(民法540条1項)。したがって、法定解除以外で、解除できる場合を設定したいのであれば、契約書に解除原因を定めることになります。このような解除を、「約定解除」といいます。 実務では、①手形・小切手の不渡り、②強制執行の申立、③破産・民事再生手続きの申立など、債務者の金銭の支払いが困難(または事実上不可能)になったと思われる事情が解除原因として設定されることが多いようです。また、これらの解除原因は、同時に上記期限の利益を喪失する事由として定めるのが一般的です。
② 無催告解除特約
さて、法定解除のうち債務者の履行遅滞に基づく解除を行う場面を想定しましょう。民法の規定によれば、債権者は、まず相当の期間を定めて履行するように催告した後でなければ、解除することができないとされています(民法541条参照)。しかし、債権者としては、「わざわざ催告をする時間も惜しい、いち早く解除したい。」と思うこともあるでしょう。このような場合には、契約条項として、解除原因がある時は「催告をすることなく解除することができる」と定めるといいでしょう。契約書のこのような定めに基づいて解除することを、「無催告解除」といいます。