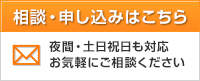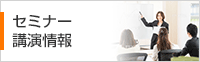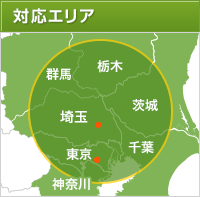賃金
第1 はじめに
賃金の支払いは、雇用主の重要な義務の一つです。なぜなら、雇用契約とは、従業員が雇用主の指揮命令下で働き、雇用主がその対価として従業員に賃金を支払う契約のことをいうからです。そこで今回のコラムでは、雇用主の方が従業員に毎月支払っている賃金についてお話しします。
第2 賃金とは
賃金は、法律に定義が定められています。すなわち、労働基準法11条は、賃金とは、従業員が「賃金、給料、手当、賞与その他の名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が従業員に対して支払うすべてのもの」と定義しています。
この定義から、賃金にあたるもの・あたらないものについて簡単に考えてみます。
まず、賃金は“雇用主が”従業員に支払うものなので、たとえばお客さんがくれるチップなどは賃金には含まれません。
また、賃金は“労働の対償”つまり労働したことの見返りであることが必要です。そうすると、たとえば家族手当や住宅手当などは除かれてしまいそうですが、実際にはそのような扱いはされていません。実務上は、労働協約や就業規則などで支給要件が明確に定められているものはすべて賃金として扱っているのです。ですから、さきほどあげた家族手当や住宅手当の他に通勤手当、慶弔給付なども賃金として扱われています。
第3 賃金の支払いに関する原則
雇用主が賃金を支払わなければ、従業員は生計を立てることができません。そこで、労働基準法は、賃金が従業員の手に確実に渡るように次のような規制をしています。
1 通貨払いの原則
賃金は、原則として「通貨」で支払わなければなりません(労働基準法24条1項本文)。ここでの「通貨」とは円のことを指します(通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律2条1項)。
ただし、この通貨払いの原則には例外が認められています
| 例外①: | 金融機関への振込という方法をとることが認められています | |
|---|---|---|
| (労働基準法施行規則7条の2第1号)。 | ||
| 例外②: | 労働協約に定めれば通貨以外のもので払うことができます | |
| (労働基準法24条1項ただし書)。 |
賃金は銀行振込にしている雇用主の方が多いと思いますが、それは例外①に基づく措置ですので、法律違反にはあたりません。
また、例外②の労働協約の定めがあれば、たとえばボーナスを現物支給にしたり、ドルで賃金を支払ったりすることも可能です。通勤定期券の現物支給も可能になります。
雇用主の方としては、例外①はもちろんですが、例外②を使用することも多いと思いますので、必要な場合は労働協約でしっかり規定しておくことが必要です。
2 直接払いの原則
賃金は、従業員に「直接」支払わなければなりません(労働基準法24条1項本文)。従業員に支払われるべき賃金は親や配偶者であっても支払うことはできませんし、従業員が賃金債権を譲渡した場合でも譲受人に支払うことはできないということです。第三者による賃金の中間搾取を防止する趣旨であるとされています。
ですので、雇用主としてはもし配偶者が本人の依頼で賃金を受け取りに来たとしても、払うべきではありません。配偶者を本人の「使者」と考えれば適法になる余地はありますが、グレーゾーンであることには違いありません。銀行口座等への賃金振込みが認められている以上その方法をとればよいのであって、むやみに第三者に支払いをしたりしないよう注意しましょう。
3 全額払いの原則
(1) 原則と例外
賃金は、原則としてその「全額」を従業員に支払わなければなりません(労働基準法24条1項本文)。ただし、この全額払いの原則にも例外が定められています(労働基準法24条1項ただし書)。
| 例外①: | 法令に定めがある場合 | |
|---|---|---|
| 所得税や社会保険料などの源泉徴収等がこれにあたります。 | ||
| 例外②: | 事業場の過半数代表との労使協定がある場合 |
(2) 賃金との相殺の可否
ここで一つ問題になるのが、例外②にあたらないと賃金債権との相殺もできないのかということです。この点について、最高裁判例は原則として相殺も全額払い原則違反となるとしつつ(最高裁昭和36年5月31日判決)、以下のような例外を認めています。
① 事務的なミスで過払いとなった賃金の清算をするための相殺(調整的相殺)
最高裁昭和44年12月18日判決(福島県教組事件)は、勤勉手当の過払いがあったため、相殺をしようとした事案において、以下の3つの要素をあげて相殺は全額払いの原則に違反しないとしました。
ⅰ)過払いのあった時期と合理的に接着した時期に相殺が行われること
ⅱ)あらかじめ従業員に予告されていること
ⅲ)額が多額にわたらないこと
② 合意に基づく相殺
最高裁平成2年11月26日判決(日新製鋼事件)は、相殺が雇用主の一方的意思で行われるのではなく、厳格かつ慎重な認定判断の下でもなお従業員の自由な意思で相殺に同意したということができるならば、相殺は全額払いの原則に違反しないとしました。
この判例からは、たとえば「会社の備品を壊したから、その分来月分の給料から引いておく」というようなことも、従業員の自由な意思で相殺に同意したといえれば可能であるといえます。逆にいうと、従業員の同意がなければ雇用主の一方的な意思表示で相殺をすることは原則としてできませんので気をつけてください。
4 毎月1回以上一定期日払いの原則
賃金は、毎月1回以上一定の期日を定めて支払わなければなりません(労働基準法24条2項本文)。この原則は、月給制以外の場合も妥当しますので、年俸制を採用している場合でも毎月1回以上賃金を支払う必要があります。
第4 休業手当
1 休業手当とは
従業員が欠勤した場合など、従業員が就業していない場合には、原則として雇用主は賃金を支払う必要がありません(ノーワーク・ノーペイの原則)。
ただし、従業員の休業が雇用主の「責に帰すべき事由」による場合には、雇用主は従業員に対し平均賃金の6割以上の手当を支払わなければなりません(労働基準法26条)。これを休業手当と呼びます。
2 民法536条2項との関係
民法536条2項によると、雇用主の「責めに帰すべき事由」によって従業員が就労できなかった場合には、10割の賃金を支払うことが求められています。この民法536条2項と労働基準法26条の休業手当はどのような関係にあるのでしょうか。
結論からいうと、民法536条2項の「責めに帰すべき事由」よりも労働基準法26条の「責に帰すべき事由」の方が広く、使用者側に起因する経営、管理上の障害も含まれると考えられています(最高裁昭和62年7月17日判決-ノース・ウエスト航空事件)。
具体例をまとめると以下のようになります。
①10割の賃金を支払わなければいけない場合
解雇無効の判決が確定したとき
②6割の休業手当を支払わなければいけない場合
機械の故障、機械の検査、原料不足、官庁による操業停止命令
③賃金の支払いをしなくていい場合
地震や台風などの自然災害や不可抗力
第5 最後に
従業員は賃金について敏感ですので、ミスがあると大きな問題になってしまうことも考えられます。また、賃金の不払いが明らかになると、企業イメージも損なわれてしまいます。そこで、まずは上記に示した4つの原則を理解したうえで、ミスのない賃金の支払いを心がけてください。