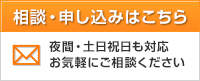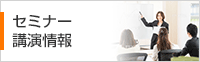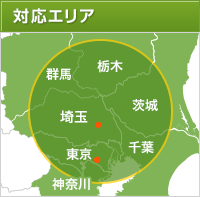最一小判H26.7.17(親子関係不存在確認請求)
2015年08月25日
平成26年7月17日最高裁第一小法廷判決(平24(受)1402号)
1. 事案の概要
Y(男)とA(女)は平成11年に婚姻しました。ところが、平成20年頃から妻Aが浮気をし、B(男)と交際を始めて性的関係を持つようになりました。そして、Aは平成21年に妊娠し子供Xを出産しました。なお、AはXが浮気相手Bの子供だと思っていました。YはAにXが誰の子か尋ねたところ、Aは「2、3回しか会ったことのない男の人」などと答えました。それにもかかわらず、YはXを自らの長女とする出生届を提出し、自らの子として監護養育しました。その後、YとAは、AをXの親権者と定め協議離婚しました。そして、AはXの法定代理人として「YとXは親子ではない」という親子関係不存在確認訴訟を提起しました。なお、DNA鑑定によって浮気相手BがXの父親である可能性は99.999998%であるとの結果が出ています。
2. 判決要旨
民法772条によって嫡出の推定を受ける子について、その嫡出であることを否認するためには、夫が嫡出否認の訴えを提起するしか方法がありません。そして、嫡出否認の訴えが提起できる期間を夫が子の出生を知ったときから1年以内に限定していることは、子の身分を不安定にしないために合理性があると最高裁は従前の立場を確認しました。
そのうえで、夫と子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであり、かつ、夫と妻が既に離婚して別居し、子が親権者である妻の下で監護されているという事情があっても、子の身分関係の法的安定を保持する必要が当然になくなるものではないから、上記の事情が存在するからといって、民法772条による嫡出の推定が及ばなくなるものとはいえず、親子関係不存在確認の訴えをもって当該父子関係の存否を争うことはできないと判示しました。
3. 実務に与える影響
本判例で問題になったのは、夫婦が婚姻中に産まれた子供について「(嫡出)推定の及ばない子」になるのはどのような場合かです。これまでの最高裁判例では、夫の不在など夫婦の同棲関係の欠如の場合に限定する立場をとっていました(外観説)。そして、今回の最高裁判例でもその立場が踏襲されました。
本判例のように、DNA鑑定で夫の子でないことが判明していても、現在父と子が一緒に暮らしていなくても、(嫡出)推定の及ばない子にはならないと判断されたことで、嫡出否認の訴えの出訴期間(子の出生を知ってから1年間)を経過した後に嫡出の推定を覆すことは非常に困難だといえるでしょう。