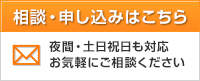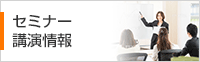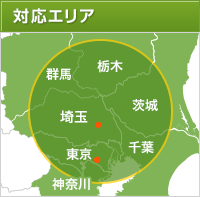債権管理と消滅時効
第1 債権管理とは
ざっくりと言ってしまえば、債権管理とは、「債権者が、自己の保有する債権を確実に回収するために作戦を練ること、および債権回収が困難になった場合を想定して次善策を講じること」をいいます。
さて、債権管理をする上で法律上重要となるのが「消滅時効」に関することです。このコラムでは、債権回収に関連した時効制度の概要、および債権管理の方法を説明します。
第2 時効制度の概要
1 消滅時効とは
「債務者も大変だろうし、払ってくれるまで待とう」といって何もしないでいるというのは非常に危険な行為です。なぜならば、債権は時の経過によって消滅してしまうことがあるからです。
債権者が、債務者に対して、売買契約に基づく代金債権を有していたとしましょう。債権者が代金の支払いを請求していないでいるということは、債務者からすれば、債権者は「(今すぐに)支払わなくてもいい」という態度をとり続けていたことになります。このような状態が長期間続いた場合、「代金が支払われていない」という状態が、いわば“常態化”します。そうすると、この“常態化”したものを後日覆すのは不合理だと考えることもできます。そこで、民法は、権利が行使できるのにもかかわらず、一定期開放置していた場合には、その権利は消滅することにしました。このような制度を、「消滅時効」といいます。債権者は早い段階で請求をすれば良かったのですから、このように考えても不都合はないでしょう。また、時間が経てば経つほど、債権の存在を証明する証拠を紛失する可能性が高くなりますから、裁判をしても勝つことは出来ず、結局「支払ってもらえない」という点では結論は変わりません。
債権管理を行うにあたっては、まずは自分が取得した債権がどのような場合に時効によって消滅してしまうのかを把握しましょう(消滅時効の要件)。そして、個々の債権の性質に応じて、時効による消滅を防止する措置をとることが重要となります。
2 消滅時効の要件
①一定の期間が経過して(「時効の完成」)、かつ②債務者が「債権は時効によって消滅した」という意思表示(「援用」)をすることで(民法145条)、債権は消滅します。以下、各要件について説明します。
① 時効の完成
消滅時効が完成するまでに要する期間(「消滅時効期間」)は、債権の種類・性質によって異なります。原則は10年ですが(民法167条1項)、会社の取引によって発生した債権(会社法5条)など商行為によって発生した債権(「商事債権」)は5年になります(商法522条)。また、売掛債権や請負代金債権は2年になります(民法173条1号2号)。
この消滅時効期間は、「権利を行使することができる時」から起算して計算します(民法166条1項)。「権利を行使することができる時」とは、法律に特別の規定がある場合(例えば、民法724条)を除き、支払期限のことをいいます。契約で支払期限を定めた場合はその日、支払期限を定めていない場合には債権が発生した日から起算します(厳密には、その日の翌日(民法140条)から起算します。)。
- ※注釈:民法改正の影響
現在進められている民法改正の議論では、この消滅時効にも焦点が当てられています。そして、消滅時効期間をなるべく統一しよう、という方向で議論が進んでおります。具体的には、①職業別の短期消滅時効(現行民法170条~174条)と商事消滅時効(現行商法522条)を撤廃し、②「権利を行使することができることを知った時」から5年間の消滅時効期間とする、という内容です。企業の取引にとっては、民法改正により影響を受ける可能性は小さいですが、念のため確認しておくといいでしょう。
② 「援用」
「援用」とは、時効によって利益を受ける者(消滅時効の場合は、主に債務者)が、自ら時効が完成したことを主張することをいいます。現在の学説および実務は、「債務者が「援用」することによって、債権の消滅という効果が生じる」と考えています。債務者は債権の消滅という時効の利益を放棄することも可能であること(民法146条反対解釈)から、債権が消滅するかどうかは債務者の意思に委ねるべきだ、と考えているからです(「私的自治の原則」)。
そうすると、単に①の時効が完成しただけでは、まだ債権の消滅という効果は発生していないことになります。したがって、理論上は、債務者が債務の援用をするまでは、債権者は債務者から債権回収をすることができることになります。
第3 債権管理の方法
1 時効を中断させる
支払期限が到来すれば、それ以降勝手に消滅時効期間が進行してしまいますので、債権者としてはなんとかそれを食い止めたいと考えるでしょう。この消滅時効期間の進行を食い止める方法として、民法は「時効の中断」を規定しています。「時効の中断」とは、一定の行為がなされると、それまで経過していた消滅時効期間をゼロに戻す制度のことをいいます。たとえば、売掛債権(消滅時効期間2年)を有するときに、あと1年で売掛債権が時効によって消滅するという時点で時効を中断すれば、その時点から再度2年の消滅時効期間が起算されることになります(民法157条1項)。
時効の中断事由は、大きく分けると①「請求」、②「差押え、仮差押え又は仮処分」、③「承認」の3つです。ここにいう①「請求」は、訴訟の提起(裁判上の請求)、支払督促、和解および調停の申立て、破産手続等の参加(民法149条~152条)といった裁判手続きを行うことをいいます。口頭で支払うよう求めたり、請求書を送ったりする行為は、法律上は「催告」と呼ばれるもので、「請求」とは区別されています。もっとも、「催告」をした後、6ヶ月以内に訴訟の提起などを行えば、時効中断の効果が生じます(民法153条参照)。そこで実務では、消滅時効期間を延ばす手段として「催告」が利用されています。例えば、「明日時効が完成してしまう。でも、正式な時効中断の手続をとっている余裕はない!」といった場合に、とりあえず権利の存在を相手方に通知(「催告」)して、6ヶ月以内に訴えを提起する(「請求」)ということがなされています。
②「差押え、仮差押え又は仮処分」とは、債権回収の実効ならしめるために、債務者の財産を確保しておくなどの裁判手続きのことをいいます(詳しくはコラム「民事保全の基礎」参照)。
上記の「請求」や「差押え、仮差押え又は仮処分」は、後の裁判手続きの経過によって時効中断の効力が認められなくなる可能性がある点に弱点があります(民法149条~155条参照)。そこで実務では、時効を中断させるには、債務者に③「承認」させるのが1番確実だといわれています。「承認」とは、債務者が債務の存在を認める行為のことを言います。例えば、残高確認書を提出させる、債権の一部を支払ってもらう、債務確認書を作成する、弁済猶予の申し出させるなどが挙げられます。債権管理の方法としては、相手方への連絡(「催告」)をしつつ、上手く「承認」にあたる行為をするよう促すともっとも効率が良いでしょう。
2 準消費貸借契約を結ぶ
別の契約で発生した「金銭その他の物」の給付を内容とする債務について、これをいわば「借り換え」のようなかたちで履行する旨の合意をすることを、準消費貸借契約といいます(民法588条)。
準消費貸借契約のメリットは、消滅時効期間を延長することができる場合がある点にあります。例えば、売買契約によって発生した売掛債権について、キチンと支払う旨の合意をすることがあるでしょう。この合意の趣旨が、単なる時効中断事由である「承認」の場合、消滅時効期間は変わらず2年になります。これに対して、この合意の内容が、売掛債権を借りたお金として扱うものであれば、売掛債権が準消費貸借契約に基づく債権に変化し、消滅時効期間が10年(商事債権であれば5年)に延びます。
3 訴えを起こす
訴えを提起して勝訴すれば、これに基づいて強制的に債権回収を行うことができます。
また時効の中断の1つとして行った裁判上の請求は、準消費貸借契約の締結と同様に、消滅時効期間を変更する効果があります。上記の売掛債権の例で言えば、単なる「承認」であれば消滅時効期間2年での再進行であったところ、訴えを提起して勝訴判決を得た場合、判決が確定した日から(民法157条2項、民事訴訟法116条)10年の消滅時効期間として再進行することになります(民法174条の2第1項)。
もっとも、訴えを提起する方法は、時効の中断や準消費貸借契約と比べると、手間と労力がかかるのが難点です。
4 時効が完成しても諦めない
上記のとおり、時効が完成したとしても、当然に債権が消滅するわけではありません。したがって、債権者は、債務者が援用するまでは、平然と債務の履行を請求するといいでしょう。仮に債務者が、「消滅時効を援用はしません。キチンと支払います。」と言って、時効の利益を放棄してくれれば、債権を回収することができる可能性があります。また、仮に債務者が時効の完成を知らなかったとしても、債権の一部を支払ったり、支払いの猶予を求めたりした場合には、債務者は時効の援用をすることができなくなるとされています(「時効援用権の喪失」)。したがって、この場合も、時効の利益の放棄がなされた場合と同様に、債権を回収することができる可能性があります。
- ※注釈:「時効の利益の放棄」と「時効援用権の喪失」の違い
時効の利益の放棄(以下、「放棄」と略します。)は、債務者が時効の完成の事実を知って行うことが前提だと考えられています。これに対して、「時効援用権の喪失」(以下、「喪失」と略します。)とは、時効の完成の事実を知らずに、上記のように客観的に時効の利益を放棄したかのような行動をとることをいいます。
放棄と喪失の違いは、その効果にあります。例えば、「A債権について、平成26年6月1日に時効が完成した。同年7月1日に、債務者はA債権の一部を支払った。」というケースを想定しましょう。このとき、「平成26年6月1日」に完成した時効を援用することができないのは、放棄であれ喪失であれ同じです。しかし、放棄の場合、金輪際A債権が時効によって消滅することがないのに対し、喪失の場合は「平成26年7月1日」から起算して再度時効完成に必要な期間が経過すれば、時効を援用することができます。
以上