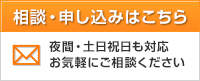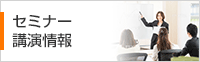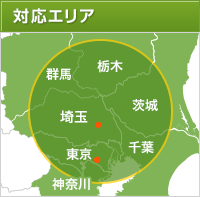会社法トラブルその1 設立無効の訴え他
第1 はじめに
コラム「会社設立の流れ」で、株式会社というロボットをつくるときは、以下のような手続を行うと説明しました。
①ロボットの設計図をつくる(=株式会社の定款を作成する)
②設計図のチェックを受ける(=公証人に定款の認証をしてもらう)
③資金や材料を集めて、ロボットを形づくる(=現金や現物で出資を受ける)
④誰が実際にロボットを操縦するかを決める(=会社の役員を選任する)
⑤ロボットとして登録(ナンバープレート)を受ける(=会社の登記をする)
以上の手続を行わなければならないと会社法で定めた趣旨は、いわゆる“欠陥ロボット”が世の中にうまれないようにするためです。しかし、どんなにチェックをしたとしても欠陥が見落とされてしまうこともあるでしょう。また場合によっては“面倒だ”と言って手続を怠ることもあるでしょう。これでは上記のような手続を定めた趣旨を没却することになります。そこで会社法では、一定の場合には、事後的に会社を無かったことにすることができる手続を用意しました。これを「設立無効の訴え」(会社法828条1項1号参照)と言います。
第2 いつ、誰が訴えを提起することができるのか
設立無効の訴えは、いつでも、誰からでも提起できるわけではありません。会社法では、株式会社の設立登記の日から2年以内に(会社法828条1項1号)、その株式会社の株主、取締役、監査役、執行役及び清算人に限り、訴えを提起することができることにしました(会社法828条2項1号)。
第3 どのような事由があれば無効となるのか
会社法の条文を探しても、どのような事由があれば無効になるのかを定めた規定はありません。一般的には、会社の設立という既に形成された事実関係をふいにしてもなお、会社をなかったことにした方がいいと言えるような重大な欠陥がある場合に、無効になると考えられています。実務では、会社の登記をする際に、キチンと手続がなされているかる審査を行うので、欠陥の存在が明らかなケースはほとんどありません。訴訟になるケースの多くは、キチンと設立手続を行ったかのように装って書面を作成して、審査を受けたような場合です。
第4 会社の設立が無効となる判決がなされたら、どうなるのか
冒頭で、設立無効の訴えは、会社の設立をなかったことにするものだ、と説明しました。もっとも厳密には、設立無効の訴えを認容する判決の以後、将来に向かってのみ無効となる=会社はなかったものとして扱われ(会社法839条)、会社設立の当初に遡る効果はありません。なぜならば、会社を設立してから判決が出るまでの間、株式会社は第三者と取引をしているのが通常ですから、既に行われた取引まで全て無効にしてしまうと法律関係が複雑になってしまうからです。
判決の効力は、訴訟の当事者間にのみ及ぶのが原則ですが(民事訴訟法115条1項1号)、設立無効の訴えが認容された場合には第三者にも判決の効力が及びます(会社法838条)。これを「対世効」と呼びます。設立無効の訴えは、この世から株式会社というロボットの存在をなかったことにするものですから、世の中全ての人に効力が及んだ方が、都合が良いからです。
設立無効の訴えが認容されると、会社の清算手続が開始します(会社法475条2号)。具体的には、継続中の取引を終了させて、債務者に対する取立てと債権者への弁済をした後に、残った財産を株主に分配します(会社法481条参照)
第5 他に救済手続はないのか
会社設立の手続が一部なされていないことにより、会社というロボットに欠陥があると主張するのが設立無効の訴えです。これに代わるものとして、会社法上の定めはありませんが、「そもそも設立登記の時点から株式会社というものは実在しなかった」と主張する方法が提唱されており、実務でも認められています。これを「会社設立不存在確認の訴え」と呼びます。設立無効の訴えとの最大の違いは、訴えることができる者およびその時期について、会社法の制限がないという点です。したがって、設立無効の訴えが提起できる者のほか、債権者など一定の利害関係がある者も訴えを提起できるとされています。また、設立登記の日から2年を経過していても、訴えを提起することができます。
しかし、会社設立不存在確認の訴えを無限定に認めてしまうと、設立無効の訴えという手続を定めた意義が失われてしまいます。そこで、会社設立不存在確認の訴えが認容されるのは、極めて限定的な場面だと言われています。具体的には、「会社設立に必要な手続が全くなされておらず、ただ登記だけがなされている場合」であるとか、「設立手続の瑕疵が著しく、瑕疵の存在が外形上明らかに認められる場合」と説明されています。
以上