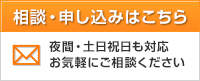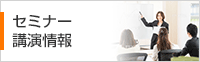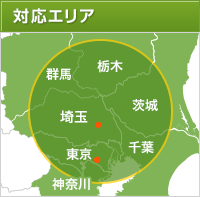会社法トラブルその7 業務執行の差止請求
第1 はじめに
例えば「A社と取引をする」という場面を想定してみましょう。このとき、①株主総会や取締役会などで「A社と取引をする」という決定をして(意思決定)、②その意思決定に基づいて代表取締役がA社と契約を締結する(業務執行)、という2つの段階を経ることになります。コラム「会社法トラブルその5 株主総会決議取消しの訴え他」やコラム「会社法トラブルその6 取締役会決議無効の訴え他」では、このうち①意思決定の手続を法律上なかったことにする手続について説明しました。
もっとも、株式会社の業務執行には、常に株主総会や取締役会の決議が先行しているわけではありません。中小企業などでは、定款の定めや取締役会による委任により、取締役個人が意思決定をして、業務を執行することがあります(会社法348条1項、362条4項参照)。このような場合には、①意思決定という手続の問題として是正手続を行うことができません。しかし、株主総会や取締役会で意思決定がなされた場合と同様に、法令・定款に違反して本来その株式会社ができないようなことをしようとすることもあり、これに“待った”をかけられないとなると株主としては困ってしまいます。そこで②業務執行の段階でも“待った”をかけられる手続を用意しました。これを「業務執行の差止請求」と呼びます。
第2 いつ、誰がどのような方法で行使できるか
6ヶ月前から引き続き当該株式会社の株式を保有している株主が、取締役等に対して業務の執行をやめるよう請求することができます(会社法360条1項)。このように請求ができる株主に制限が加えられている趣旨は、いわゆる“クレーマー”のような株主による権利行使によって株式会社の運営が妨げられるのを防ぐ点にあります。もっとも、非公開会社では、家族経営のような規模の小さい株式会社が多く、“クレーマー”がでる可能性が低いことから、「6ヶ月前から」という制限が外されています(会社法360条2項)。
なお監査役設置会社では監査役(会社法385条1項)、委員会設置会社では監査委員(会社法407条1項)も、業務執行の差止請求をすることができます。
また業務執行の差止請求は、裁判所に対する訴えをもって行う必要性はなく、直接取締役に対して口頭で止めるよう進言する、という方法でも行使することができます。
第3 どのような場合に差止めができるか
「株式会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為」(その「おそれ」がある場合を含む)があり、かつ②「株式会社に著しい損害が生ずるおそれがあるとき」に、株主は取締役等の行為を差し止めることができます(会社法360条1項)。以下、それぞれの要件をもう少し掘り下げて説明します
①「株式会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為」
「株式会社の目的」とは、株式会社というロボットの活動限界、いわば“リミッター”のようなものです。そして、どのような“リミッター”が設定されているかは、株式会社の定款を見れば分かります(詳しくは、コラム「定款に記載すべき事項」)。定款記載の目的の範囲(=“リミッター”)を超えるようなことを行わせると、株式会社に“不具合”が生じるのは明らかですから、差止請求の対象となります。
「法令若しくは定款」も同様に株式会社の活動可能な範囲を画するものですから、法令・定款違反行為も差止請求の対象となります。この「法令」は、会社法の条文はもちろん、株式会社やそれを運用する取締役のできることを規律するあらゆる法令が含まれます。
②「株式会社に著しい損害が生ずるおそれがあるとき」
業務執行によって、単に株式会社が損害を被るだけでは足りず、「著しい損害」が発生するおそれがあるときにのみ、株主による差止請求が認められます。株主は、取締役に株式会社の経営を一任している立場にあるので、極力経営に対する干渉は避けようとする趣旨です。そして、仮に損害が発生するとしても、取締役に対する事後的な損害賠償請求(会社法423条1項参照)でも十分処理できるような場合には、わざわざ事前の差止めをする必要性はない、と判断されます。
なお、監査役設置会社又は委員会設置会社の場合には、「著しい損害」ではなく、株式会社に「回復することができない損害」が生ずるおそれがあるときのみ差止め請求をすることができます(会社法360条3項)。この規定は、差止請求を行使する者の優先順位を決めるためのものだと言われています。すなわち、監査役や監査委員がいる場合には、株主ではなく監査役や監査委員が取締役等の行為に“待った”をかけること予定していることを意味します。実務上も、「著しい損害」と「回復することができない損害」とで明確に線引きしているわけではなく、株主が差止請求できる場合が極めて限定されるという程度の運用になっているようです。
差止め請求が認められると、対象となった業務執行行為が今も継続する場合は当該行為を中止し、「行為をするおそれがある場合」には実行してはならない義務が、取締役等に生じます。他方で、1回限りの取引など、業務執行行為が既に行われて終了している場合には、差止請求をすることができません。
第4 取締役の独走を防ぐためには
業務執行の差止請求訴訟を提起しても、判決が確定するまでは取締役に対する拘束力は生じません。よって、取締役が、株主からの差止請求を無視して、職務を執行しようと思えばできてしまいます。このような自体を避けるためには、「職務執行停止の仮処分」の申立を行うと良いでしょう。
「職務執行停止の仮処分」とは、違法として申し立てられている行為を行ってはならないという仮の地位を定めるものです(民事保全法23条2項)。そして、訴訟に比べると、簡易かつ迅速に裁判所の判断がなされる点に大きなメリットがあります。
もっとも、上記仮処分が認められるためには、①被保全権利と②保全の必要性が一応あると裁判官に推測(「疎明」、民事保全法13条1項)させる必要があります。ここに言う①被保全権利は、上記の差止請求権のことですので、上記の要件を裏付ける資料を提出することになります。他方で、仮の地位を定める仮処分を行う上での②保全の必要性とは、「債権者に生じる著しい損害」または「急迫の危険」を避ける必要性があることを言います。実務上は、被保全権利である業務執行の差止請求権の存在が疎明されれば、株式会社に「著しい損害」(会社法360条1項)が生じるおそれがあることが推測され、取締役が違法行為を行ってしまえば差止め請求が無意味になってしまうとして、「急迫の危険」があると判断されることが多いようです。
職務執行停止の仮処分が認められると、裁判所が取締役に対して、“取締役は、○○(=違法行為)を行ってはならない”と命じることになります。
以上