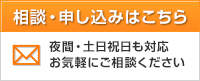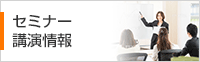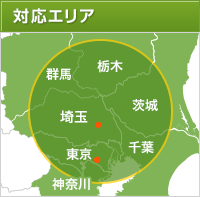組織再編と事業譲渡
第1 事業譲渡とは
事業譲渡とは、会社が取引行為として「事業」を他人に譲渡する行為のことを言います。事業譲渡は、「会社の一事業が他の会社に移転する」という点で、合併や会社分割と類似しますが、概念・目的が違うものとしてあるとして扱われています。少しかみ砕いて説明しましょう。
合併や会社分割は2つ以上の会社が協力して、“結合”してよりよい性能を有する会社を生み出すことを目的とした「制度」だと表現することができます。つまり、法律で「制度化」されることではじめて認められたものです。したがって、“結合”によるインパクトは大変大きいですが、その分様々な手続をパスしなければなりません。
これに対して事業譲渡は、本来個別に取引することができる一定の権利義務その他の財産を、いわば1つの“パッケージ”として取引するようなものです。したがって、行為の性質としては組織再編のような特別なものではなく、個別の取引行為の延長線上にあると言えます。もっとも、“パッケージ”としてまとめて財産などが承継されることは会社に対するインパクトが大きいので、後述の通り法律によって一定の規制がなされています。
このように合併・会社分割と事業譲渡というのは、法律で特別に認められた制度なのか取引行為としての性質を有するものなのかという点で異なります。このような違いがあることから、合併・会社分割と比較して、事業譲渡には以下のようなメリット・デメリットがあると言われています。この点を踏まえて、合併・会社分割と事業譲渡のいずれを選択するか検討することをおすすめします。
【事業譲渡のメリット】
- 事業を承継させる手続が簡便で、迅速に実施することができます(後述)
合併や会社分割の手続で必要な契約書等の備置き、債権者異議手続、登記などは不要です - 事業譲渡の相手方は、会社である必要はありません
- 事業譲渡に“不具合”があった場合、「~無効の訴え」のような特別な訴えを提起することなく、無効を主張することができます
【事業譲渡のデメリット】
- 個別の権利義務や財産の承継の合意とは別に、取引に付随する手続(対抗要件の具備など)を個別に行う必要となります
- 労働契約承継法の適用を受けないので、事業の移転に伴って労働者も当然に引き継がれるのではなく、個別の同意が必要となります(民法625条1項)
- 事業を譲り受けた者が交付する対価は、原則として現金になります
- 許認可を受けた地位までは承継されないので、事業を譲り受けた会社は新たに許認可を取得する必要があります。
第2 事業譲渡の手続
上記の通り、事業譲渡は、個別に取引できるようなものを“パッケージ化”して承継させる行為ですから、いわば本来であれば経営判断を行う取締役ないし取締役会が意思決定をして契約をすれば、それだけで効力が生じるはずです。しかし、会社の権利義務・財産がまとまった形で承継されることは、会社に対するインパクトが大きいことから、以下のような規制がなされています。
①出資者の承認を受ける
会社の存続に関わるような重大な取引になることもあるでしょうから、原則として出資者であり会社の所有者である株主の承認を得る必要があります。したがって、会社法では、原則として事業譲渡の効力が生じる日までに株主総会の特別決議による承認を受けることを要求しました(会社法467条1項、309条2項11号)。但し、わざわざ株主の意思を確認する必要性がない(または低い)場合、具体的には、相手方が大株主で株主総会の帰趨が明らかな場合には、株主総会の特別決議による承認は不要となります(「略式事業譲渡」(会社法467条1項))。
会社の事業の全てを譲渡する場合には、事業を譲り受ける相手方も株主総会の特別決議による承認が必要です(会社法467条1項3号参照)。但し、対価として交付する財産の価額が小さい(純資産の20%以下)場合には、譲受会社及びその株主に対するインパクトが小さいとして株主総会の特別決議による承認が不要となります(「簡易組織再編」(会社法468条2項))。
②不服のある者への対応
事業譲渡を行う会社を介して、その影響を受ける者のうち、株主についてのみ配慮すべき規定が置かれています。具体的には、会社は、事業譲渡の効力が生じる20日前までに事業譲渡行う旨を公告又は株主に対して通知しなければなりません(会社法469条3項4項)。その上で、「反対株主」(組織再編の場合と同様です。詳しくはコラム「組織再編の手続」を参照)は、株式の買い取りを請求することができます(会社法469条1項本文、2項)。
第3 事業譲渡と債務の承継
1 事業譲渡と債務の関係
事業譲渡は、上記の通り、譲渡会社に帰属していた権利義務その他の財産を、1つの“パッケージ商品”として取引するものです。この権利義務その他の財産を、どのように“パッケージ化”するかは、当事者の意思によって決められます。したがって、「プラスの財産だけ譲渡して、マイナスの財産(=債務)は譲渡会社に残す」という合意も可能です。
もっとも、このような合意は当事者間のみで行われ、譲渡された事業に係る取引相手(=債権者)は、事業譲渡が行われたことは知りえません。仮に知りえたとしても、事業の実施形態に変化がなければ、債務も譲受会社に承継されたものと考えるのが一般的です。このような債権者の“期待”を保護するために、会社法は一定の場合には債務が承継されたのと同様に扱うものとしました。すなわち、「商号を引き続き使用」という事業の実施主体の交替がないような外形がある場合には、債権者は上記のような“期待”が発生するとして、譲受会社は「事業によって生じた債務」を負うものとされています(会社法22条1項)。条文上は「商号」とされていますが、屋号を続用している場合など、債権者の上記“期待”が生じる場面にも会社法22条1項が適用(または類推適用)されと考えられています。
- ※商号を続用しない場合の債務の承継
- 上記以外にも、債務の承継があったと債権者が誤信するような事情がある場合には、債権者の“期待”を保護する必要があります。会社法では、債務を承継する旨の合意の有無にかかわらず、譲受会社が「債務を引き受ける旨の広告」をした場合には、債務が承継されたのと同様の扱いがなされます(会社法23条1項)。
- ※「債務が承継されたのと同様」の意味
- 正確には、「譲渡会社から譲受会社に債務が移転した」のではなく、「譲受会社も譲渡会社と一緒に債務を弁済する」ことになるものです。但し、事業譲渡の日(会社法22条3項)または「広告があった日」(会社法23条2項)から2年以内に、債権者が譲渡会社に対して請求または請求の予告をしない場合には、「譲渡会社の責任」は消滅するとされています。これによって、債権者は譲受会社にしか請求できなくなるので、事実上は債務が承継されたのと同様の扱いになります。
2 譲受会社が債務の承継を望まない場合に必要な処置
譲受会社としては、債務は承継しないものと考えていたのに、債務は承継されたものとして扱われては困ります。そこで、「商号」(これに類する外形を含む)を続用しながら債務の承継を回避するためには、以下のような処置をする必要があります。
まずは、事業譲渡契約書に債務を承継しない旨の記載をしましょう。これは後日譲渡会社から、債務は承継されたとの主張を封じる趣旨です。
その上で、遅滞なく、①「債務の弁済する責任を負わない旨の登記」(商業登記法31条参照)、または②債権者に対する債務の弁済する責任を負わない旨の通知を行います。これによって譲受会社は、譲り受けた事業に係る従前の債務を弁済する責任を免れます(会社法22条2項)。