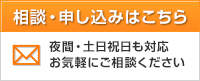2015年08月26日
1. 事案の概要
本件は、亡Aの遺言執行者であるXが、Yに対し、亡Aが死亡時に有していた未収金債権(以下「本件債権」という。)の支払を求めた事案です。
平成12年6月24日、Yは、Xに対し、本件債権にかかる債務の存在を承認しました。本件債権は、商行為によって生じた債権ですので、上記承認により同日から5年の経過(平成17年6月24日)により消滅時効が完成することになります(商法522条)。
Xは、Yに対して、平成17年4月16日到達の内容証明郵便で本件債権の支払の催告をした上で、同年10月14日、Yを被告として、本件債権の一部(3億9761万円余りのうち、5293万円余り)の支払を求める訴えを提起しました(以下、「別訴」という。)。これに対し、Yは、本件債権の一部は、相殺によって消滅した、と主張しました。平成21年4月24日、裁判所は、Yの主張を認めた上で、本件債権の額は7528万円余りであると認定して、Xの請求を全部認容する旨の判決を言い渡しました。同判決は、同年9月18日に確定しました。
平成21年6月30日、Xは、Yを被告として、別訴で請求していなかった本件債権の残部の支払を求める訴えを提起しました(以下、「本件訴え」という。)。これに対し、Yは、本件訴えにかかる本件債権の残部については、平成17年4月16日到着の催告から6箇月以内に民法153条所定の措置を講じなかった以上、本件債権の残部については消滅時効が完成している、と主張しました。
2. 判決要旨
最高裁は、いわゆる明示的一部請求において時効中断の効力が生じるのは、請求がなされた一部の範囲に留まり、「残部について、裁判上の請求に準ずるものとして消滅時効の中断の効力を生ずるものではない」とする従来の最高裁の立場を踏襲しました。
その上で、本判決は、「残部につき権利行使の意思が継続的に表示されているとはいえない特段の事情のない限り」、先行する一部請求の訴えの提起は、「残部について、裁判上の催告として消滅時効の中断の効力を生ずる」と判示しました。その結果、債権者は、一部請求にかかる訴訟の終了後「6箇月以内に民法153条所定の措置を講ずることにより、残部について消滅時効を確定的に中断することができる」ことになります。
ただし、催告が繰り返されることでいつまでも時効が完成しないのでは、時効制度の趣旨に反するおそれがあります。そこで最高裁は、「消滅時効期間が経過した後、その経過前にした催告から6箇月以内に再び催告をしても、第1の催告から6箇月以内に民法153条所定の措置を講じなかった以上は、第1の催告から6箇月を経過することにより、消滅時効が完成する」として、催告の繰り返しによる時効中断効を制限しました。
そして、Xが第1の催告にあたる平成17年4月16日の催告から6ヶ月以内に、残部について民法153条所定の措置をとらなかった以上、本件債権の残部は消滅時効が完成しているとして、Xの本件訴えを棄却しました。
3. 実務に与える影響
本判決は、①明示的一部請求(本件における別訴)は、残部についての裁判上の「催告」(民法153条)として効力が認められること、②裁判上の催告か裁判外の催告かを問わず、催告の繰り返しによって時効の完成を阻止することは出来ないことを、最高裁として初めて判断した点に大きな意義があります。企業の取引実務では、債権の時効の管理として、債権の一部のみの請求を行ったり、裁判外の催告を行ったりすることは少なくないと思います。このような債権管理を行う場合には、本判決の判断に注意する必要があるでしょう。
以上
2015年08月26日
1. 事案の概要
本件は、XらとYらとの共有に属する土地(以下、「本件土地」という。)について、Xらが、Yらに対して、共有物分割を求めた事案です。
本件土地は、X1会社(72分の30の共有持分)、X1の元代表者であるX2(72分の39の共有持分)、X2の妻A(72分の3の共有持分)の共有となっていました。
| 30/72 |
X1(会社) |
| 39/72 |
X2(X1の元代表者) |
| 3/72 |
A(X2の妻) |
また、本件土地上にはX1会社やX2名義の建物が建っていました。
平成18年9月、Aが死亡しました。その結果、本件土地についてAが有していた共有持分(以下、「本件持分」という。)は、Aの相続人に相続され、夫のX2及び子のX3、Y1、Y2の4名の遺産共有状態となりました。
| 30/72 |
X1(会社) |
| 39/72 |
X2(X1の元代表者) |
| 3/72 |
A(X2の妻)が死亡。X2及び子のX3、Y1、Y2の4名の遺産共有状態 |
Xらは、Yらに対して、本件持分をX1会社に取得させ、X1会社がAの共同相続人らに対して賠償金を支払う方法(いわゆる全面的価格賠償)という内容の共有物分割を提案したのですが、Yらは拒絶しました。
そこでXらは共有物分割の訴えを提起しました。これに対して、Yらは、X2名義の共有持分の2分の1もAの相続財産に含まれると主張する他、本件土地の価格を争いました。
一審は、価格賠償によると賠償金が各相続人に確定的に支払われしまい遺産分割の対象とはならないとから、価格賠償による方法はとりえないとして、競売による分割を採用しました。
これに対し、原審は、一審を破棄し、賠償金は相続人の共有となることから、価格賠償による方法でも問題ないとして、全面的価格賠償の方法による分割を採用しました。
2. 判決要旨
最高裁は、以下のように判示して、Xらの主張を認めた原審の判断を維持しました。
- その1.
- 遺産共有持分と他の共有持分とが併存する場合において、その共有関係を解消する方法として「裁判上採るべき手続は民法258条に基づく共有物分割訴訟であり、共有物分割の判決によって遺産共有持分権者に分与された財産は遺産分割の対象となり、この財産の共有関係の解消については同法907条に基づく遺産分割によるべき」である。
- その2.
- 全面的価格賠償の方法による共有物分割の判決がなされた場合には、「遺産共有持分権者に支払われる賠償金は、遺産分割によりその帰属が確定されるべきもの」であり、遺産共有持分権者は、「遺産分割がされるまでの間これを保管する義務を負う」。
- その3.
- 裁判所は、全面的価格賠償の方法による共有物分割の判決をする場合には、「その判決において、各遺産共有持分権者において遺産分割がされるまで保管すべき賠償金の範囲を定めた上で、遺産共有持分を取得する者に対し、各遺産共有持分権者にその保管すべき範囲に応じた額の賠償金を支払うことを命ずることができる」。
3. 実務に与える影響
同じ「共有」であっても、民法上その共有関係の解消の方法は、相続を原因とする遺産共有の場合は遺産分割手続(民法907条2項)、他の共有の場合は共有物分割手続(民法258条)と、異なる手続によることが規定されています。本判決は、このように共有関係の解消手続が異なる遺産共有と他の共有とが併存する場合に、その共有関係の解消の在り方を示したものとして、実務上重大な意義があります。
なお本判決は、遺産共有状態のまま、遺産共有以外の共有関係を解消しようとする場合の手続について判示したものだ、という点に注意が必要です。言い換えれば、遺産共有と他の共有が併存する場合には、常に共有物分割手続を行わなければならない、というわけではありません。例えば、遺産分割によって遺産共有状態を解消した後に、共有物分割の手続を行う、という2段階の手続を行うことも可能です。
以上
2015年08月25日
1. 事案の概要
本件は、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の2分の1とする民法の規定(民法900条4号但書前段。以下、「本件規定」という。)の憲法適合性が争われた事案です。
平成13年7月、被相続人Aが死亡しました。当時、相続人としては、Aの妻であるB、AとBの子であるX1、X2、AとBの子で亡Cの代襲相続人であるX3及びX4、並びにAとその内縁の妻Dの子であるY1及びY2がいました。
平成16年11月、Bが死亡し、X1、X2、X3及びX4(以下、まとめて「Xら」という。)がBを相続しました。その結果、Aの相続財産に関して各相続人の法定相続分は、X1とX2が各48分の14、X3とX4が各48分の7、Y1とY2(以下、まとめて「Yら」という。)が各48分の3になります。
その後、Xらは、Yらに対して、法定相続分に基づいて計算した具体的相続分での遺産分割を求めて、調停及びそれに引きつつ審判を申し立てました。これに対して、Yらは、一貫して、本件規定は憲法14条1項に反し無効であると主張しました。
2. 判決要旨
最高裁は、本件規定は、「遅くともAの相続が開始した平成13年7月当時においては、立法府の裁量権を考慮しても、嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する合理的な根拠は失われていた」として、憲法14条1項に違反している判示しました。主な理由として、「父母が婚姻関係になかったという、子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、その権利を保障すべきであるという考えが確立されてきている」ことを挙げています。
そして、平成13年7月に死亡したAの相続に関しては、本件規定は「憲法14条1項に違反し無効でありこれを適用することはできない」とし、遺産分割をやり直させるため原審に差し戻しました。
なお本決定は、過去に本件規定を合憲とした判例を変更するものではない旨述べると共に、本件の「相続の開始時から本決定までの間に開始された他の相続につき、本件規定を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判、遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではない」として、本件規定を無効とする判断の遡求効を制限しています。
3. 実務に与える影響
本決定を受けて、平成25年12月11日、本件規定を削除した新しい民法が公布・施行されました。この改正民法は、平成25年9月5日以降に開始した相続について、適用されることになっています。そうすると、平成25年9月4日以前に開始した相続について、本決定との関係でどのように処理すべきなのかが問題となります。この問題は、相続開始時点が、本件規定が違憲だとされた平成13年7月以降の場合と、平成13年7月より前の場合とに区分されます。
①相続開始日が平成13年7月から平成25年9月4日の場合
上記判旨の通り、平成13年7月以降に相続が開始した場合であっても、「遺産の分割の審判その他の裁判、遺産の分割の協議その他の合意等」(以下「遺産分割の合意等」という。)により「確定的なものとなった法律関係」には、本件規定を違憲とした本決定は影響しないとされています。裏返せば、未だ「確定的なものとなった法律関係」とは言えない場合、いわば相続の問題が未解決の場合には、本件規定を違憲無効とした本決定の判断を前提として、相続に関する紛争を処理することになります。
なお何をもって「確定的なものとなった法律関係」と言えるかについては、本決定では明言されていません。この点に関しては、今後の判例・学説の解釈に委ねられることになるでしょう。参考として、法務省は、次のような見解を示しています。
- (ⅰ)遺産分割の審判が確定している場合や遺産分割協議が成立している場合には、「確定的なものとなった法律関係」といえる
- (ⅱ)相続財産が、当然分割となる過分債権の場合には、相続開始によって「確定的なものとなった法律関係」とは言えない。相続人全員が相続分にしたがい払戻しを受けた時点で、「確定的なものとなった法律関係」となる。
※詳しくはhttp://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00143.html
②相続開始日が平成13年6月以前の場合
本決定は、過去に最高裁が「相続開始時点での本件規定の合憲性を肯定した判断」を変更しないとしています。過去に本件規定が合憲だとした最高裁判例のうち、もっとも相続開始時点が遅いのは平成12年9月です(最判平成15年3月31日)。そうすると、この2つの判例で判断されていない期間(平成12年10月~平成13年6月)に関しては、未だ本件規定が合憲か否か分からないことになります。よって、この期間に開始した相続をめぐる紛争では、本件規定の合憲性を争うことができると考えることもできるでしょう。もっとも、本決定が、本件規定の違憲無効の判断の遡求効を制限している趣旨に照らすと、実質的には「遺産分割の合意等」がなされていない未解決の場合でなければ、本件規定の合憲性を争うことは難しいと思われます。
以上
2015年08月25日
1. 事案の概要
本件は、認知者自身が血縁関係の不存在を理由として認知無効の訴えを提起した事案です。
X男は、平成15年3月、フィリピン国籍のA女と婚姻しました。平成16年12月、Xは、A女の連れ子3人のうち末子のY(当時8歳)を認知する旨の届出をしました。X男とYとの間には血縁関係がなく、認知当時Xはそのことを知っていました。
X男とA女は、平成17年10月から同居を開始したものの、一貫して不仲だったため、平成19年6月ごろから別居しました。それ以降、X男はYとほとんど会っていません。
そこでX男が、Yに対して、認知無効の訴えを提起しました。Y側は、血縁関係がないことを知って認知した者が、認知無効の訴えを提起することは許されないと争いました。
2. 判決要旨
最高裁は「認知者は、民法786条に規定する利害関係人に当たり、自らした認知の無効を主張することができるというべきである。この理は、認知者が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした場合においても異なるところはない。」と判示して、X男の上記認知は無効とした広島高裁の判断を維持しました。その理由として、①認知する事情は様々であるから、認知無効の訴えを一切許さないと解釈するのは相当ではないこと、②血縁関係がないことを理由に認知が無効になることがある以上、子の保護の観点から、認知者自身による認知無効の主張を一律に制限する理由は乏しいこと、③認知による父子関係が発生する以上、認知者自身が、認知の効力について強い利害関係があることは明らかであること、を挙げています。
3. 実務に与える影響
本判決は、認知者による認知無効の主張を認める一方で、具体的な事情によっては権利濫用の法理(民法1条3項)により制限されることがあることに言及しています。そして、本判決の多数意見からは明らかではありませんが、Xの認知無効の主張が認められた背景には、Yにはフィリピン国籍の実父その他の親族がいることから、仮にXとの親子関係がなくなっても、重大な不利益は被らないという特殊な事情があったと考えられています。したがって、本判決の結論から、一般論として「親子関係は、血縁の有無が重視される」「血縁関係がなければ、認知者自身による認知無効の訴えができる」と評価するのは難しいでしょう。
なお近年の民法改正の議論を見ると、認知者による認知の無効の主張を制限する立法を行おうとする傾向があります。また、最新の判例でも、血縁の有無よりも法律上の子の利益・地位の安定を優先したと評価できるようなものがあります(最判平成26年7月17日)。このような事情に照らすと、血縁の有無が、親子関係の存否を決定づける要素にはならないのではないかと思われます。
以上
2015年08月25日
1. 事案の概要
本件は、元夫が、娘との面会交流の実施を拒む元妻に対して、間接強制を求めた事案です。
X男とY女は、平成16年5月に婚姻し、平成18年1月に長女Aが誕生しました。平成22年11月、X男とY女は離婚をし、Y女がAの親権者になりました。
平成24年5月、Y女はX男がAと面会交流をすることを許さなければならないとする審判がなされ、同年6月に確定しました。その審判では、面会交流の方法として、具体的には以下のようなことが定められました。
- ①月1回、毎月第2土曜日の午前10時~午後4時、Aの福祉を考慮してX男の自宅以外でX男が定めた場所で面会交流を行う
- ②X男及びY女は、Y女の自宅以外の場所でAを引き渡す
引渡場所は、当事者間の協議が調わないときは、所定の駅改札口付近とする
Y女は、X男とAとの面会交流に立ち会わない
上記審判の後、Y女は、XのAとの面会交流の求めに対して、Y女はAが拒絶しているとの理由で応じませんでした。そこでX男は、上記審判に基づき間接強制を求めました。
2. 判決要旨
最高裁は、面会交流に関する審判について、「性質上、間接強制をすることができないものではない。」とした上で、「監護親に対し非監護親が子と面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判において、面会交流の日時又は頻度、各回の面会交流時間の長さ、子の引渡しの方法等が具体的に定められているなど監護親がすべき給付の特定に欠けるところがないといえる場合は、上記審判に基づき監護親に対し間接強制決定をすることができる」と判示しました。
そして、本件においては、「面会交流の日時、各回の面会交流時間の長さ及び子の引渡しの方法の定めにより抗告人がすべき給付の特定に欠けるところはないといえるから、本件審判に基づき間接強制決定をすることができる。」としました。
3. 実務に与える影響
本決定は、審判で面会交流の給付の内容が具体的に定められている場合には、裁判所は審判に基づき間接強制決定をすることができると判示した点に大きな意義があります。今後、監護親が面会交流の求めに応じない場合に備えるのであれば、少なくとも、本決定で列挙された3つの要素を審判事項で明示しておく必要があるでしょう。
なお実務では、本件のY女のように、子供が拒絶しているとして、監護親が面会交流の実施に応じないことがあります。この点につき本決定は、裁判所は子供の心情に十分配慮して面会交流に関する審判を行っている以上、後に子供が拒絶していたとしても、間接強制を否定する理由にはならない旨を判示しています。言い換えれば、子供が嫌がっているとしても、それだけでは面会交流の実施を拒む理由にはならないことになります。もし子供が面会交流を拒絶しているのであれば、監護親は、面会交流に関する調停・審判をやり直すしかありません。本判決は、この点について判示した点にも注目すべきでしょう。
以上
2015年08月25日
1. 事案の概要
本件は、ゴルフ場に利用されている複数の土地(以下、まとめて「本件土地」という。)の地上権設定契約及び賃貸借契約設定契約に関して、その地代及び賃料の減額について争われた事案です(以下、X・Yの請求の一部は省略する。)。
昭和63年7月、本件土地を所有するYは、Aとの間で、ゴルフ場経営を目的とする地上権設定契約及び賃貸借契約を締結しました。
その後、上記契約に基づく地上権者及び賃借人たる地位は、転々譲渡されました。平成18年9月、Xは、Yの承諾を得て、本件土地の地上権者及び賃借人たる地位を取得しました。それ以来、Xは、本件土地を利用してゴルフ場を経営しています。
平成19年3月、Xは、Yに対して、本件土地の地代及び賃料について減額の意思表示をしました。その後、Xは、Yに対して、減額された地代及び賃料の確認を求めて訴えを提起しました。地代及び賃料減額の根拠として、Xは①借地借家法11条1項と②事情変更の原則(民法1条2項)を主張しています。これに対して、Yは、Xに対して、未払い分の地代及び賃料の支払いを求めました。
2. 判決要旨
最高裁は、借地借家法は、「建物の所有を目的とする土地の利用関係を長期にわたって安定的に維持する」趣旨であるから、建物所有を契約の目的としておらず、かつ「建物の所有と関連するような態様で使用されていることもうかがわれない」本件においては、借地借家法11条を類推適用して地代及び賃料を減額することはできないと判示しました。
その結果、Xの請求は棄却され、Yの請求のみが認容されました。なお、Xの事情変更の原則の主張も、これを基礎付ける事情が認められないとして退けています。
3. 実務に与える影響
本判決は事例判例に過ぎませんので、最高裁が、一般論として、借地借家法11条の類推適用が認められるのか、認められるとしてどのような場合に、どの範囲で認められるのか(1項のみなのか、2項3項も含むのか)について明らかにしたものではありません。この点、過去に、当該契約の土地利用の目的から建物所有が契約の主たる目的だと認められる場合には、借地借家法の適用があるとした判例があります(最判昭和42年12月5日)。この判例と本判決を踏まえると、借地借家法の類推適用の余地があるのは、①建物所有が契約の従たる目的の場合と、②契約の目的ではないが借地人が土地上の建物を所有する場合だと考えられます。具体的な要件や適用範囲については、今後の学説・実務の課題と言えるでしょう。
以上
2015年08月25日
1. 事案の概要
本件は、Aが、債務整理を依頼したY弁護士の説明が不十分だったとして、Yに対して、慰謝料等の支払を求めた事案です。
AとYは、消費者金融5社に対する債務整理を目的とする委任契約を締結しました。Yは、消費者金融5社に対して、過払い金の返還を請求したり、元本債務の一部減額という方法での和解を提案したりしました。その結果、3社から過払い金の返還を受け、その過払い金の一部を原資として他の1社と和解を成立させました。Yは、Aに対して、和解が成立しなかった残りの1社については、そのまま放置して当該債務に係る債権の消滅時効の完成を待つ方針(以下、「時効待ち方針」という。)を採るつもりであることを説明しました。
その後、Aは、Yの債務整理に不安を抱き、Yを解任しました。Aが、改めて別の代理人に債務整理の委任をしたところ、最後の1社とも和解が成立しました。
そこでAは、Yの債務整理の方針についての説明義務を怠ったとして、債務不履行に基づく損害賠償を求める訴えを提起しました。なお第1審係属中にAが死亡したため、妻Xが訴訟承継している。
2. 判決要旨
最高裁は、Yは「委任契約に基づく善管注意義務の一環として、時効待ち方針を採るのであれば、Aに対し、時効待ち方針に伴う上記の不利益やリスクを説明するとともに、回収した過払金をもって…債務を弁済するという選択肢があることも説明すべき義務を負っていた」として、Yの説明義務違反を認めました。その背景として、次のような事情があったことを認定しています。
- ①時効待ち方針には、債務整理の最終的な解決が遅延するという不利益がある
- ②消費者金融が残債権の回収を断念し、消滅時効が完成することを期待し得る合理的な根拠がなく、提訴される可能性があった
- ③一旦提訴されると遅延損害金も含めて敗訴判決を受ける公算が高いというリスクがあった
- ④他の消費者金融から回収した過払い金で残債無を弁済する方法によって、最終的な解決を図ることも現実的な選択肢として十分に考えられた
3. 実務に与える影響
本判決は、弁護士の説明義務について初めて判断したものです。事例判例ではありますが、依頼者に重大な影響を及ぼす方針を採用するに際しては、依頼者がその方針を十分理解してその当否を判断できるように、多角的かつ丁寧な説明が求められることを示した点で、実務上重要な意義があります。なお、補足意見で、田原裁判官が、時効待ち方針は原則として許されない旨を指摘している点にも注目すべきでしょう。
以上
2015年08月25日
1. 事案の概要
本件は、保証人に対する保証債務の履行請求に対して、従前保証債務を履行していた保証人が主債務の消滅時効の完成を主張した事案です。
Xは、A銀行との間で、BがA銀行に対して負う債務(以下、「A債務」)を保証する旨の契約を締結しました。Yは、Xとの間で、保証委託に基づきBがXに対して負担すべき求償金債務について連帯保証する旨の契約を締結しました。
平成12年9月、XはA銀行に対してA債務を代位弁済しました。その結果、Xは、Bに対する求償金債権を取得しました(民法459条1項)。
平成13年6月にBは死亡しました。Yは、単独でBを相続して、その旨をXに告げました。その後Yは、上記連帯保証契約に基づく保証債務の履行として弁済を継続して行いました。
平成22年1月、Xは、Yに対して、保証債務の残部の履行を求めました。これに対して、Yは、主たる債務である求償金債権が、その発生時から5年が経過し、時効によって消滅しているから、保証債務も附従性によって消滅すると主張しました。
2. 判決要旨
最高裁は、「保証人が主たる債務を相続したことを知りながら保証債務の弁済をした場合、当該弁済は、特段の事情のない限り、主たる債務者による承認として当該主たる債務の消滅時効を中断する効力を有する」と判示しました。保証債務の弁済は、通常、主債務の存在を前提としていますので、主債務者兼保証人の地位にある者による保証債務の弁済は、主債務の存在を承認するものに他ならないと考えられるからです。また。保証人としての地位に基づいて主債務を承認することを含むような行為を行いながら、主債務者としての地位に基づいてこれと異なる行動をすることは想定し難いことも理由としています。
その結果、Yの主債務の消滅時効完成による消滅の主張は認められず、Xの請求が全部認容されました。
3. 実務に与える影響
本判決のキーポイントは、①相続によって“主債務者件保証人という地位”にある保証人であること、②保証人が、主債務を相続したことを認識して保証債務の弁済を行ったこと、の2点です。したがって、仮に本件でYの他に相続人がいた場合、Yが保証債務の弁済を行っても、保証人としての地位のない他の相続人との関係では、時効中断効はないと考えられます。また、仮に本件でYがA死亡の事実を知らずに保証債務の弁済を行っていた場合も、同様に時効中断効は認められないと考えられます。なお、本判決は、「特段の事情」がある場合には、時効中断効は認められないとしていますが、この「特段の事情」がいかなる事情なのかは明らかではなく、今後の学説・実務での解釈に委ねられています。
このように債務の承認と相続がからむ問題は、学説上も実務上も従来あまり意識されてきませんでした。高齢化社会を迎え、ますます相続をめぐる紛争の発生が予想される現代社会において、本判決は大変意義のあるものだといえるでしょう。
以上
2015年08月25日
1. 事案の概要
本件は、金銭消費貸借契約の借主が、消滅時効期間を経過した債権を自働債権とした相殺等により、貸金債権が消滅したと主張した事案です。
平成14年1月、Xは、Aとの間で、457万円を借り入れる旨の金銭消費貸借契約(民法587条)、及びX所有の不動産について根抵当権設定契約(民法176条)を締結しました。この金銭消費貸借契約には、支払いを遅滞したときは当然に期限の利益を喪失する旨の特約(いわゆる期限の利益喪失特約)がありました。その後、Aは、Yに吸収合併され、Aの貸主たる地位はYが承継しました。
Xは、A及びYに対して、上記金銭消費貸借契約に基づく貸付金について、継続的に返済を行っていました。しかし、平成22年7月分の返済が滞ったため、Xは、上記特約に基づき期限の利益を喪失しました。なお、この時点における貸金債権の残額は、約189万でありました。
XとYは、過去に金銭消費貸借契約を締結しており、その際過払い金が約18万円ありました。そこでXは、平成22年8月、Yに対して、過払い金の返還請求権(民法703条)を含む合計約28万円の債権を自働債権として、貸金債権と対当額で相殺する旨の意思表示をしました。その後、Xは、Yに対して、上記相殺が有効であることを前提にして、貸金債権の残額に相当する約167万円を返済しました。なおYは、平成22年9月、上記過払い金返還請求権の消滅時効を援用する意思表示をしています。
その後、Xは、Yに対して、被担保債権である貸金債権が相殺及び弁済によって消滅したことを理由として、上記根抵当権設定登記の抹消登記手続を求めて訴えを提起しました。これに対してYは、過払い金債権は時効により消滅する以前に貸金債権と相殺適状になかった以上、Xの相殺は無効であると主張し、貸付金の残額の支払いを求めました。
2. 判決要旨
最高裁は、まず「既に弁済期にある自働債権と弁済期の定めのある受働債権とが相殺適状にあるというためには、受働債権につき、期限の利益を放棄することができるというだけではなく、期限の利益の放棄又は喪失等により、その弁済期が現実に到来していることを要する」と判示しました。そうすると、本件において、過払い返還請求権(自働債権)と貸金債権(受働債権)が相殺適状になったのは、Xが期限の利益を喪失した平成22年7月になります。
その上で、民法508条に基づき、時効によって消滅した債権を自働債権として相殺をするためには、「消滅時効が援用された自働債権はその消滅時効期間が経過する以前に受働債権と相殺適状にあったことを要すると解される」と判示しました。そして、本件では、上記相殺適状になった時点よりも前に、過払い金返還請求権の消滅時効期間は経過していたので、民法508条は適用されず、Xの相殺は効力を有しない、と結論づけました。その結果、貸金債権は残っているので、Xの根抵当権設定登記抹消登記手続請求は認められず、Yの貸金返還請求のみが認められました(貸金の残額を明らかにするため、原審に差し戻されました)。
3. 実務に与える影響
本判決の解釈方法は、相殺と期限の利益の喪失に関する民法の規定を、文言通りに解釈したものだ、と評価することができます。したがって、本判決の解釈方法は、相殺一般に通じる解釈方法であり、その射程は広いと考えられます。
なお実務上、債権管理の一貫として相殺という方法が採られることは少なくありません。そして、本判決によって、自働債権だけでなく受働債権についても、期限の利益の放棄や喪失により現実に弁済期が到来していなければ、相殺が認められないことが明らかになりました。本判決は、債権管理の在り方として、自働債権の時効だけでなく受働債権の弁済期についても配慮を促したという点で、実務上も大きな意義があるでしょう。
以上
2015年08月25日
平成26年7月17日最高裁第一小法廷判決(平24(受)1402号)
1. 事案の概要
Y(男)とA(女)は平成11年に婚姻しました。ところが、平成20年頃から妻Aが浮気をし、B(男)と交際を始めて性的関係を持つようになりました。そして、Aは平成21年に妊娠し子供Xを出産しました。なお、AはXが浮気相手Bの子供だと思っていました。YはAにXが誰の子か尋ねたところ、Aは「2、3回しか会ったことのない男の人」などと答えました。それにもかかわらず、YはXを自らの長女とする出生届を提出し、自らの子として監護養育しました。その後、YとAは、AをXの親権者と定め協議離婚しました。そして、AはXの法定代理人として「YとXは親子ではない」という親子関係不存在確認訴訟を提起しました。なお、DNA鑑定によって浮気相手BがXの父親である可能性は99.999998%であるとの結果が出ています。
2. 判決要旨
民法772条によって嫡出の推定を受ける子について、その嫡出であることを否認するためには、夫が嫡出否認の訴えを提起するしか方法がありません。そして、嫡出否認の訴えが提起できる期間を夫が子の出生を知ったときから1年以内に限定していることは、子の身分を不安定にしないために合理性があると最高裁は従前の立場を確認しました。
そのうえで、夫と子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであり、かつ、夫と妻が既に離婚して別居し、子が親権者である妻の下で監護されているという事情があっても、子の身分関係の法的安定を保持する必要が当然になくなるものではないから、上記の事情が存在するからといって、民法772条による嫡出の推定が及ばなくなるものとはいえず、親子関係不存在確認の訴えをもって当該父子関係の存否を争うことはできないと判示しました。
3. 実務に与える影響
本判例で問題になったのは、夫婦が婚姻中に産まれた子供について「(嫡出)推定の及ばない子」になるのはどのような場合かです。これまでの最高裁判例では、夫の不在など夫婦の同棲関係の欠如の場合に限定する立場をとっていました(外観説)。そして、今回の最高裁判例でもその立場が踏襲されました。
本判例のように、DNA鑑定で夫の子でないことが判明していても、現在父と子が一緒に暮らしていなくても、(嫡出)推定の及ばない子にはならないと判断されたことで、嫡出否認の訴えの出訴期間(子の出生を知ってから1年間)を経過した後に嫡出の推定を覆すことは非常に困難だといえるでしょう。