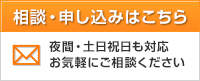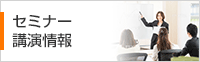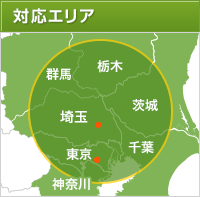担保権設定契約についての注意点
第1 はじめに
1 担保とは
「担保」とは、債権者が債務者から金銭の支払いを受けることができなくなった場合に、代わりの人や物から回収することができることにした仕組み、ないし権利(担保権)のことを言います。なお担保制度に概要については、コラム「担保制度の概要」、コラム「物などを利用した担保(物的担保)について」、コラム「人を利用した担保(人的担保)について」を参照してください。
このコラムでは、契約によって物や債権についての担保権が生じる場面(いわゆる物的担保)を想定して、契約書にどのような事項を記載すべきかを説明します。例えば、「持家や自動車を担保にしてローンを組む」という場面を想像してみてください。
- ※注:物的担保の契約類型
- 契約によって発生する物的担保(約定担保物権)のうち、民法上明確な規定があるのは、質権(民法342条)と抵当権(民法369条1項)の2つのみです。これ以外の約定担保物権は、法律の規定がなければ、新たな創出することはできないとされています(物権法定主義(民法175条))。
もっとも実務では、上記2つ以外にも、本来は担保としての性質を有しない契約(主に所有権の移転に関する契約)を利用して、事実上「物を担保にする」という効果が発生するような工夫を行っています。一般的に、「譲渡担保」「仮登記担保」「所有権留保」と呼ばれているものです(いわゆる非典型担保)。
これらの担保は、法形式の違いはありますが、物的担保を設定する際の契約書に記載すべき内容は概ね共通します。このコラムでは、このような違いにかかわらず、物を担保とする契約の総称として「担保権設定契約」と呼ぶことにします。
2 担保権設定契約の要素
物を担保にすると、債権者は、その物から債権の回収を図ることができる権利が発生します。そして、物に対する権利というのは、どのような物(目的物)を対象としたどのような権利(権利の内容)なのかで特定されます。したがって、契約書には①目的物と担保権の内容に関する記載は必ず必要です。
物を担保にするということは、自分の所有する物で「借金の肩代わり」をするようなものです。物の所有者としては、自己の物が際限なく「肩代わり」になる可能性があるままだと不安でなりません。したがって、②どの「借金」(被担保債権)を担保するものなのかも特定することも必要となります。
さらに担保となる物の所有者としては、いついかなる場合に自分の所有する物が「借金の肩代わり」に供されるのか気になるところです。したがって、③どのような場合に「肩代わり」となってしまうのか、その際どのような手続になるのか、についても記載しておくことが重要となります。
第2 担保権設定契約の契約条項
1 目的物と担保権の内容の特定
(1) 目的物について
契約書には、何を担保権設定契約の目的物にするのかを特定するに足りる事項を記載しなければいけません。不動産であれば、所在、地番・家屋番号、面積などの登記記載事項で足ります。動産であれば品名、型式・年式、カタログ番号などで特定することができます。実務では、複数の動産(集合物)をまとめて担保の目的物にすることがあります。この場合には、対象となる動産の種類の特定事項に加えて、動産の所在場所と動産の量的範囲の記載が必要だとされています。
なお担保権設定契約は、目的物を処分する権原(主に所有権)が当事者でなければならず、権原のない者が行った場合には、原則としてその担保権は無効であるとされています。したがって、債権者は、後のトラブルを避けるためにも、事前に不動産登記等を確認するなどして、担保権設定契約の相手方が目的物について担保権を設定する権原を有しているかを確認しておく必要があるでしょう。
(2) 権利の内容について
上記で説明したとおり、一口に物的担保といっても、様々な法形式があります。そして、その法形式によって、担保目的物からの債権回収の細かな手続・方法が変わってくることがあります。したがって、これから締結する担保権設定契約がどのような担保権を設定するものなのかを契約書で明らかにしなければなりません。
2 被担保債権の特定
被担保債権が特定されていない担保権設定契約は無効だと解されているので、被担保債権の内容ないし範囲を契約書に明記しなければなりません。
債権は、①当事者及び②発生原因事実によって特定されます。
当事者とは、被担保債権の債権者及び債務者のことです。例えば、「甲の、乙に対する…」といった書式になります。
債権の発生原因事実は、債権の発生日と債権の種別・内容によって特定されます。例えば「平成○年○月○日付の金銭消費貸借契約に基づく貸金債権(債権額○○万円、返済期日平成平成○年○月○日、利息年○%)」といった書式になります。継続的な取引に基づいて発生する債権をまとめて被担保債権とすることも法律上許されています(民法398条の2第1項参照)。このような場合には、対象となる債権の範囲(“○○の取引によって発生する債権”)と上限額(「極度額」)を定めなければなりません。
3 実行手続き
一般的には、①債務者が債務を履行しない事態の発生(弁済期の徒過)、②目的物の売却・競売手続の実行、③②の代金から債権を回収、という流れになります。契約書には、個々の事情に応じて、どのように債権回収を行うのかを記載しておくといいでしょう。例えば、以下のようなものが挙げられます。
①債務者が債務を履行しない事態の発生(弁済期の徒過)
一定の事由がある場合には、直ちに実行手続きに移行する旨の合意をすることができます(いわゆる「期限の利益喪失」条項と同様。詳しくはコラム「契約書の内容」参照)。この場合、どのような事由があると実行手続きに移行するのかを契約書に明記する必要があります。
②目的物の売却・競売手続の実行
担保の目的物を売却してその代金から債権を回収する、という方法ではなく、債権者がその物の所有権を取得することで債権の回収をはかる、という方法も許されています。このような処理をする場合には、どの時点で所有権が移転することにするのかを契約書に明記する必要があるでしょう。
③代金から債権を回収
債権者が取得することができるのは、あくまで被担保債権の額の範囲内です。どのような債権の回収方法を選択するにしても、被担保債権の額を超えて債権者が利益を得ることは許されません。したがって、特に非典型担保を利用する場合には、被担保債権を上回る分の差額については担保目的物の所有者に返還する、という条項(いわゆる清算条項)を記載する必要があります。
4 その他
(1) 対抗要件の具備について
担保物権の帰属について相争うような紛争が生じた場合に、民法では「対抗要件」の具備をもってその優劣を決定するものとしています(民法177条、178条参照)。例えば、同時に2人の者が抵当権の設定を受けた場合、登記の先後によって優劣が決まります。ここにいう「対抗要件」というのは担保目的物によって異なり、抵当権であれば不動産の登記、譲渡担保であれば譲渡担保登記ファイルへの登記(動産債権譲渡特例法3条1項)などになります。これらの手続をいつ、誰の負担で実施するのかを契約書に記載しておくといいでしょう。また既に優劣が決定している場合(たとえば、これから設定する抵当権が二番抵当権である場合など)は、その順位も契約書に記載して、確認するようにしましょう。
(2) 禁止条項
後のトラブルを避け、法律関係が複雑にならないように、所有者による担保目的物の利用・処分を禁止・制限する条項を設けておくといいでしょう。例えば、担保目的物の無断譲渡・賃貸を禁止する、担保目的物の改造・損壊を禁止する、管理状況を報告させるなどが挙げられます。
(3) 被担保債務が消滅した場合の処理
たとえば被担保債権が弁済によって消滅した場合、担保権を存続させておく必要はありませんから、当然に消滅するものと考えられています。もっとも、法律上担保権が消滅したとしても、登記等が残っていると悪用される可能性があります。したがって、被担保債権が消滅した場合の処理の方法、具体的には登記の抹消や物の返還等に関する手続・費用の負担に関しても定めておくといいでしょう。